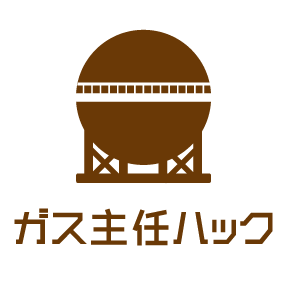ガス技術
製造
(ガ)問1
都市ガスの原料に関する次の記述のうち、いずれも誤っているものの組合せはどれか。
(イ) LNG は貯蔵中に外部からの入熱により沸点の低いメタンを主とするボイルオフガス(BOG)が発生するため、メタン以外の成分の濃度が高まる。(ロ) LPG が流出した場合、気化ガスは空気の1.5~2倍と重く、着火源の多い地表面に滞留するため、取扱いには十分注意しなければならない。(ハ) LNG 貯槽で層状化が発生した場合には、他の貯槽への移送、貯槽内での循環や撹拌等を行ってはならない。(ニ) バイオマスは生物が光合成によって生成した有機物であるため、燃焼することにより放出される二酸化炭素は、ライフサイクルの中では大気中の二酸化炭素を増加させない。(ホ) LNG 配管においてボーイングが起こると、外部からの入熱による温度の上昇により内部の圧力が上昇し、フランジ等の弱い部分が破壊されるおそれがある。
(4)ハ、ホ (5)二、ホ
(ガ)問2
都市ガスの製造設備に関する次の記述のうち、いずれも誤っているものの組合せはどれか。
(イ) オープンラック式LNG気化器は、サブマージド式LNG 気化器と比較して運転費が安いため、ベースロード用に用いられることが多い。
(口) 円筒形ガスホルダーは、表面積が少ないので球形ガスホルダーに比べ、単位貯蔵ガス量あたりの使用鋼材量が少ない。
(ハ) LNG 配管は、必ず溶接継手構造とし、フランジ部を設けてはならない。
(ニ) LNG サテライト基地用ローディングアームは、金属パイプとスイベルジョイントを組合せたものであり、各スイベルジョイントを支点として自由に動くことができる。
(ホ)LNG ローリーは、二重殻式横置円筒型の超低温容器が固定されており、内槽は低温じん性の高いステンレス鋼が使用されている。
(4)ロ、ホ (5)二、ホ
(ガ)問3
都市ガスの熱量調整と燃焼性管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 液-ガス熱量調整方式は、LNG を LPG で熱量調整する場合、LNG を気化させた天然ガス (NG)中に LPG をスプレーして直接 LPG を混合気化させる方式である。
(2) 液-液熱量調整方式は、LNG を LPG で熱量調整する場合、-160 °C の LNG に LPG を混合するため、LNG 以外の成分の凍結による閉そく対策等が必要となる。
(3) 高発熱量のガスを空気で希釈すると燃焼速度(MCP)は低下するが、ウォッベ指数は変化しない。
(4) ガスーガス熱量調整方式は、LNG を LPG で熱量調整する場合、LPG を気化させるための設備及び熱源が必要で、ランニングコストが高い。
(5) 空気により低圧の供給ガスを希釈する場合、供給ガスが燃焼範囲に入らないよう空気の混合量を管理する。
(ガ)問4
都市ガスの付臭に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 炎光光度検出器(FPD)付ガスクロマトグラフ法で検出される付臭剤成分は、テトラヒドロチオフェン(THT)、ターシャリーブチルメルカプタン(TBM)、ジメチルサルファイド(DMS)等の有機硫黄化合物である。
(2) パネル法は、あらかじめ適正に選定された臭気の判定者(パネル) 4名以上により、においの有無を判定し、ガスの臭気濃度を求める方法である。
(3) 滴下注入方式の注入量の調整は、ニードル弁等によって行うが、手動式の場合はその精度は低いため、流量変動の少ない小規模の付臭設備に用いられる。
(4) 蒸発式付臭設備のバイパス蒸発方式では、蒸発した付臭剤の混合比率を一定に保つことができるので、一般に混合付臭剤が使用される。
(5) TBM の特徴は、認知閾値が低く、においのインパクトが強いことがあげられる。
(ガ)問5
都市ガスの製造において使用される計測機器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) バイメタル式温度計は、2種の金属接点間の温度差に応じた熱起電力が発生することを利用したものであり、広い範囲の測定ができる。
(2) ブルドン管式圧力計は、構造が簡単で測定範囲が広いが、クリープやヒステリシスが生じやすい。
(3) 膜式流量計は、容積式の一種であり、気体の測定に適している。
(4) ピトー管による流量測定は、外側の管に孔がある二重構造の管を流体中に挿入して、先 ・ 端部と側面部の差圧を測定し流量に換算する。
(5) 静電容量式レベル計は、蒸留水のような誘電率の小さい液体には不向きである。
(ガ)問6
都市ガス製造設備の耐震設計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 耐震設計には、構造設計のほか、地震により異常が発生しても安全性を確保できるような安全設計、災害の発生や拡大を防止するための防災設計等が含まれる。
(2) レベル1地震動は発生確率が低いが高レベルの地震動。レベル2地震動は発生確率が高い地震動である。
(3) 高さのある設備やたわみやすい構造物で、静的震度法を適用すると過小な耐震評価となるおそれがあるものには、修正震度法を適用する。
(4) 重要度の高い設備や、1次固有振動数が小さく、それ以上の固有振動数を無視できない設備には、動的応答解析法を用いて安全照査を行う場合がある。
(5) 大型の平底円筒型貯槽では、内部液体のスロッシング(液面揺動)周期が数秒から十数秒となるので、スロッシングに対する耐震設計も必要となる。
(ガ)問7
都市ガス製造設備の巡視・点検に関する次の記述について、【 】の中の(イ)~(ホ)内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
製造設備は、これらの設備を正常に維持するため、【(イ)】等を作成し、それに従って 製造設備の管理を行う。製造設備に係る巡視・点検周期やその方法は、【(ロ)】に定める
内容を満足するほか、設備の運転状態を表す監視項目や点検内容も考慮し、製造所の 【(ハ)】に合わせ決定する。
設備に異常を発見した場合は応急処置を施すとともに、速やかに【(二)】に努めなけれ ばならない。万が一、復旧に時間を要する場合は、製造設備の【(ホ)】などを行って、ガスの供給に影響を及ぼさないようにする。
(1) (イ)維持管理基準(ロ)保安規定(ハ)操業実態(二)機能回復(ホ)稼働調整
(2) (イ)維持管理基準(ロ)保安規定(ハ)修理履歴(二)運転停止(ホ)復旧措置
(3) (イ)維持管理基準(ロ)技術基準(ハ)修理履歴(二)機能回復(ホ)復旧措置
(4) (イ)運転管理基準(ロ)保安規定(ハ)修理履歴(二)運転停止(ホ)稼働調整
(5) (イ)運転管理基準(ロ)技術基準(ハ)操業実態(二)機能回復(ホ)復旧措置
(ガ)問8
製造所における保安設備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 電気設備を可燃性ガスを通ずる設備やそれらの設備の付近に設置する場合は、その設置場所の状況に応じた防爆性能を有するものでなければならない。
(2) 可燃性ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物は、ボイラー等の火気を取り扱う設備まで – の最低限必要な距離が定められている。
(3) 可燃性流体を通ずる塔槽類には避雷設備を設ける。
(4) 高圧のもの若しくは中圧のもの又は液化ガスを通ずる製造設備で過圧が生ずるおそれのあるものには、爆発戸、破裂板、水封器等を設ける。
(5) 自家発電装置、予備蓄電池又は電力以外の動力源を保有して、停電時に保安上重要な設備の機能が失われたり、危険状態にならないようにする。
(ガ)問9
環境対策に関する次の記述のうち、いずれも誤っているものの組合せはどれか。
(イ) LNG、LPG は硫黄分や窒素分等をほとんど含まず、都市ガスの製造段階において大気環境に負荷を与える硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)の発生はほとんどない。
(口) 排ガス再循環方式は、燃焼排ガスの一部を燃焼用空気に混入して炉内に送り込み、NOxの発生量の減少を図るものである。
(ハ) 水素イオン濃度指数(pH)は、純水で7付近であり、pHが7よりも小さくなればアルカリ性、逆に7よりも大きくなれば酸性となる。
(ニ) 燃焼温度、空気比等を適正に管理することにより、ばいじん発生量を減少させることができる。
(ホ)電気エネルギーの管理では、力率を0に近づけると省エネルギー効果を上げることができる。
(4)ロ、ホ(5)ハ、ホ